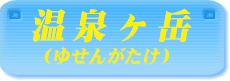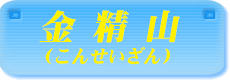|
【往路】 桐生から国道122号線を走り、足尾を抜けて奥日光へ向かいます。途中みどり市東町にある「丸美屋自動販売機コーナー」朝飯を食べました。ここはうどんやトーストなどレトロな自販機が有る事で有名です。ここを目当てで来る人も居る位です。この日は6時前に寄ったのですが私たちの他に2人が利用していました。
日光までは走っている車も少なかったのですが、いろは坂に向かう道に合流すると一気に車は増えてきます。紅葉が見頃を迎えた奥日光へ向かう車です。まだ7時前だというのに竜頭ノ滝には駐車場待ちの車列が出来ていてこれにはビックリです。その先の戦場ヶ原も駐車場は一杯になっています。この時点で気温は0度近くになっており、戦場ヶ原は霜で真っ白です。朝日が当たって幻想的に光っており車を止めて写真を撮りたい気分でしたが、ここは我慢して先へ進みます。これから向かう金精トンネルの駐車場は、普段から土日は早い時間に一杯になる事が多い様です。紅葉時期で久々に良い天気になったこの日はその事を考慮して早く家を出たのですが、奥日光の混雑ぶりを見て心配になってしまいました。登山口近辺にはトイレは無いので、湯ノ湖でトイレに寄り金精トンネルに向かいました。 |
|

丸美屋自動販売機コーナー
|

金精山とトンネル駐車場
|
|
【7:20】 金精トンネル駐車場
金精トンネル入口のすぐ左側が駐車場になっています。そこには既に20台程の車が入っており満車です。その脇のスペースにも埋まっています。でも幸いな事に、道の反対側にある7、8台止められるスペースは半分以上空いていました。早速そこに駐車して準備を始めます。
【7:40】 登山開始
駐車場の奥が登山口になっており、気持ち良い秋晴れのなか登山を開始します。温泉ヶ岳と金精山へはここから一旦金精峠まで登り、そこからそれぞれの山頂まで往復します。
金精峠に向かう登山道は急登である事で有名です。徐々に傾斜が増すのではなく、いきなり急登になるので体が慣れず疲れます。岩や段差のある丸太階段、壊れかけの階段などバリエーションに富んでいます。息を切らしながら約30分登ると小さな社が見えてきました。そこが第一の目的地である金精峠です。 |

登山口
|
|

金精峠への急登
|

金精峠への急登
|
|

壊れかけの梯子
|

金精峠直下
|
|

金精山と金精神社
|

金精峠
|
|

金精峠より見る男体山
|
【8:10】 金精峠
いきなりの急登を登り終え、金精峠に到着です。
この峠は各方面への分岐点となっております。ここから北方面(金精トンネルから登って場合は右手)へ行くと、温泉ヶ岳や根名草山でその先は奥鬼怒温泉郷に続いています。南方面は金精山や五色山を経由して五色沼や日光白根山へ続いています。そういう事で多くの人が下の駐車場を使っているのだと思います。
また登山道も登って来たコースとは別に菅沼登山口からのコースもあります。白根山と同じ登山口で標高差は100m程多く時間も倍近くかかりますが、傾斜はそれ程急ではなくゆっくり登りたい方は菅沼からが良いと思います。
峠は細長く平らになっているので、休む所は多くあります。金精神社の社が鎮座し、後ろには金精山を従えていました。奥日光側は木が無く、良く見渡せます。朝なので逆光になってしまっていますが、男体山や光る湯ノ湖が見えていました。片品側は木が茂っていて見渡せません。 |
|

男体山と湯ノ湖
|

下に見える駐車場
|
|

温泉ヶ岳に向けて出発
|

温泉ヶ岳への登山道
|
|
【8:20】 温泉ヶ岳へ出発
金精峠で10分程休んでから温泉ヶ岳へ向けて出発します。温泉ヶ岳は金精山と比べて100m近く標高が高いのですが、急登はそれ程無い様なのでこちらを先に登る事にしました。登山道は確り整備されており歩き易くなっています。この辺は気温が氷点下になったらしく、霜柱が立っている所もありました。
途中木が無くなり展望が開けた所から、金精山とその奥に日光白根山、そしてその右には菅沼が青く見えていました。少し先に進むと今度は奥日光側が開け、男体山と中禅寺湖が見えてきました。
【9:05】 温泉ヶ岳山頂への分岐
金精峠から45分で温泉ヶ岳山頂への分岐に到着します。この分岐を左に登っていくと温泉ヶ岳山頂で、そのまま進むと登山道は根名草山へ続いています。 |

登山道の霜柱
|
|

金精山と日光白根山
|

温泉ヶ岳登山道から見える菅沼
|
|

男体山と中禅寺湖
|

温泉ヶ岳山頂への分岐
|
|

温泉ヶ岳山頂手前
|

温泉ヶ岳山頂
|
|

温泉ヶ岳山頂
|
【9:15】 温泉ヶ岳山頂到着
分岐からは今までの登山道とは違い、道は細く傾斜も若干増してきています。分岐の矢印には15分と書いてあったのですが、10分程で温泉ヶ岳の山頂へ到着しました。
山頂はそれ程広くはありません。10数人で一杯になってしまう程度だと思います。周りには高い木が生えており、展望があるのは北西と東の一部のみです。北西方面は雲も無くスッキリ遠くまで見渡せます。根名草山、燧岳、至仏山、四郎岳などが見えていました。東方面は若干雲が出ており遠くは霞んでいます。女峰山や刈込湖が見えました。
ここの山頂には25分程居ましたが、結局他の登山者とは会いませんでした。 |
|

北西方向の眺望
|

東方面に小さく見える刈込湖
|
|

下山開始
|

山頂分岐
|
|
【9:40】 下山開始
下山は登って来た道をそのまま戻ります。登山時は3人位の登山者とすれ違っただけでしたが、下山時は団体さんも含め10人以上の登山者とすれ違いました。車が多かった割には温泉ヶ岳へ登る人は少ない様です。登りでは気づかなかった周りの景色も、下りでは余裕が出来てそれが見える事が良くあります。
【10:25】 金精峠到着
温泉ヶ岳山頂から約45分で金精峠に戻って来ました。登りには55分かかっているので、下りは10分の短縮です。この時は水分やエネルギー補給などで5分程度休み、今度は金精山に向けて出発します。
登り始めの登山道は比較的緩やかです。温泉ヶ岳の方では余り見えなかった紅葉も、こちら側では所々見る事が出来ました。 |

金精峠到着
|
|

金精山へ向けて出発
|

登山道にある紅葉
|
|

近くに迫る金精山
|

石の上を渡る登山道
|
|

傾斜のキツクなる登山道
|
最初は緩やかな上り坂だった登山道も、しばらくすると傾斜は徐々に増していきます。岩壁が目の前に迫ってくると登山道は右へそれ北側から登る事になります。
ここからの登山道が少し苦労します。始めはトラバースする感じで、石の上を歩いたりして回り込みます。やがて登山道は山の上に向かい始め、最終的には岩場の直登になります。それでも大変な所にはロープや梯子が設置されているので、ゆっくり登れば危険ではありません。ただ登り辛い急登が連続しますので、息が切れ足に疲労は蓄積します。
そんな急登も15分位で終わり、登山道の傾斜は徐々に緩やかになります。そのまま少し登ると稜線に出て、再び男体山と湯ノ湖が目に飛び込んできました。ここまで来れば山頂は間近ですので、稜線を歩いて山頂を目指します。 |
|

ロープを使って岩場登り
|

急斜面に設置されている梯子
|
|

急登終了
|

稜線に出たので山頂間近
|
|

金精山山頂
|

金精山山頂
|
|
【11:15】 金精山山頂到着
稜線を3分程歩くと金精山の山頂へ到着です。ここの山頂も余り広くはありません。でも先客は居なかったのでゆっくり休めました。
温泉ヶ岳の山頂からは日光方面は見えませんでしたが、ここからは邪魔する木は無く良い眺望です。金精峠に比べ標高も高く遮る山も無くなったので、男体山から続く日光連山が見えていました。湯ノ湖も良く見え、その先の男体山麓には戦場ヶ原が広がっていました。そして左手には先程登った温泉ヶ岳が、肩を並べる様に聳えていました。
日光側とは対照的に片品側は木が茂っています。菅沼や丸沼、白根山などは見る事が出来ませんでした。また、この時間になると空には雲が多くなってしまいました。男体山の山頂部分は雲に隠れています。多分地形の関係で、奥日光周辺のみ雲がかかってしまった様です。
ここで休んでいる間に数組登頂してきましたが、皆さんゆっくり休まず直ぐ下山していきます。白根山方面からも2組位来たと思います。 |

山頂から見た温泉ヶ岳
|
|

男体山と湯ノ湖
|

男体山
|
|

湯ノ湖
|

走って来た峠道
|
|

下山開始
|

下山も一苦労
|
|

金精峠到着
|
【11:55】 下山開始
登り辛いという事は、下り辛いという事でもあります。急登の場所は特に慎重に下ります。腿や膝へのダメージも、登りと同じかそれ以上のような気もします。
【12:20】 金精峠
登りは45分かかった所を、25分で下りて来ました。ここでは水分補給をするのみで下山を続けます。ここからも急な下りが続くので、足の疲労は更に蓄積されて来ました。それでも登りの時のは気付かなかった紅葉が目に入ってきます。疲れを忘れられる瞬間です。
【12:45】 駐車場へ無事帰還
駐車場の車に入れ替わりはありましたが、相変わらず満車です。更に路肩にも何台か止まっていたので、実際には増えていました。
この後車の中で着替えを済ませ、周りの写真を少し撮って、帰路につきました。 |
|

金精峠より
|

下山時に気づいた紅葉
|
|

紅葉と男体山
|

金精トンネル駐車場へ無事帰還
|
|

金精トンネル周辺の紅葉
|

丸沼湖畔より
|
| 【復路】 帰りは金精トンネルを抜けて、丸沼に寄りました。前にも一度この時期に来たことがありますが、その時に比べると紅葉の色付きが今一の様な気がしました。その後は丸沼ダムと園原ダムで息子がダムカードを貰い、根利経由で桐生へ戻りました。 |
【ひとこと】 今回は1日で2座のぐんま百名山を登る事が出来ました。金精峠を起点に両山をピストンで登る人は多くいる様です。確かに片方だけでは物足りない気もしますが、1回下りてから登り直すというのは同じ標高差を登り続けるよりも疲れます。それから金精峠までの急登は覚悟していましたが、金精山への急登は予想外でした。
紅葉に関しては、ハッキリ言ってダメでした。金精峠までとその周辺には所々ありましたが、稜線上では殆ど無かったです。これが今年だけなのか、いつもなのかは分かりません。 |